Warning: Undefined array key "token" in /home/xmd/hug-full.com/public_html/wp-content/themes/hugfull/template-parts/content.php on line 12
妊娠中に気を付けたい 感染症 。「母子感染」や妊婦健診で調べる感染症はどんなものがある?【医師監修】
2022.02.21
- 7月アンケート
- 麻疹
- 風疹
- 水痘(水疱瘡)
- リステリア症
- 伝染性紅斑(リンゴ病)
- 尖圭コンジローマ
- ヘルペス
- 腟カンジダ症・トリコモナス・淋病
- サイトメガロウイルス
- B群溶血性レンサ球菌
- 性器クラミジア
- HTLV-1
- 梅毒(梅毒トレポネーマ)
- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)
- C型肝炎ウイルス
- 感染症
- B型肝炎ウイルス
- トキソプラズマ症
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
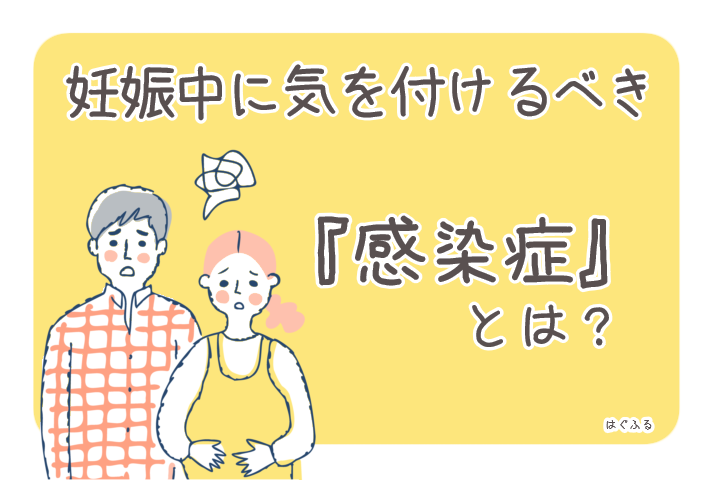
妊娠中に気を付けたい 感染症について 【監修】井畑 穰(いはた ゆたか) 産婦人科医
感染症の中には、妊娠中にかかると、おなかの赤ちゃんに影響が及んだり、早産や流産を引き起こしたりするものがあります。
妊娠中は細菌やウイルスに対する抵抗力が弱くなっているので、普通なら問題ないレベルの接触でも悪化してしまうことがあり、一層の注意が必要です。
早期発見・早期治療のために、妊婦健診で行われる感染症検査をきちんと受けるようにしましょう。
母子感染とは?:3つの経路『胎内感染』『産道感染』『母乳感染』
お母さんが持っている細菌やウイルスが赤ちゃんに感染することを「母子感染」あるいは「垂直感染」といい、大きく分けて次の3つの感染経路があります。
【妊娠中の感染】-胎内感染-
妊娠中に胎盤や羊水を経由して感染します。
【分娩中の感染】-産道感染-
分娩が始まって産道を通るときに感染します。
【出産後の感染】-母乳感染-
出産後、授乳をすることで感染します。
産道からしかかからない感染症であれば、妊娠中に治療を行うことで赤ちゃんへの感染を防ぐことができ、帝王切開でも回避ができます。
しかし、1つの感染経路だけではなく、複数の経路からかかる感染症もありますので、実際には個々の症例で適切に対応することが必要です。
また、お母さんが感染した場合、お母さん自身の症状がほとんど無くても、赤ちゃんに深刻な合併症(不顕性感染)が生じることもあります。症状のない感染を知ることはとても難しいのですが、妊婦健診をきちんと受け、感染症の知識を深めることで、母子感染の確率を減らすことができます。
▶参考:「妊娠と感染症」(厚生労働省)
(2022年1月閲覧:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/ninpu-03.html)
▶参考:「母子感染を知っていますか?」(厚生労働省)
(2022年1月閲覧:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken16/dl/06_1.pdf)
感染症の調べ方:抗原検査と抗体検査について(スクリーニング検査)
新型コロナでも話題になりましたが、細菌やウイルスの感染の有無を調べる方法は大きく分けて2つ、抗原検査と抗体検査があります。
「抗原」検査では、細菌やウイルスの有無を調べます。
培養検査やPCR検査も広い意味では抗原検査と考えて結構です。
一方、人は感染した後、体の中で病気を治すための武器である「抗体」を作ります。
その抗体の有無を調べるのが抗体検査です。抗体があれば感染しにくく、また感染しても重症化しにくくなり、これを免疫と呼びます。
抗体があると、「調べた時点より数日以上前に感染した」ということは分かりますが、現在も感染しているかどうかは分かりません。
抗体がものすごく多ければ、今まさに感染したばかりで、体がウイルスと戦っている最中なのかもしれません。
スクリーニング検査という言葉がよく使われますが、これは症状のない人を対象にして、疑いのある人を速やかに見つけるための検査です。
妊婦健診はおおむねスクリーニング検査になります。
見つけ漏らしを極力少なくするため、正常な人でも検査に引っかかる確率が高くなっているものもあります。
スクリーニング検査で陽性でも、追加検査で問題ないことはよくありますので、陽性でも心配せずに追加検査を受けましょう。
妊婦健診で調べる感染症(産科ガイドラインで推奨されているもの)
B型肝炎ウイルス
妊婦健診ではHBs抗原検査をします。
陽性のほとんどが、ウイルスは持っているけれども症状は出ていない「キャリア(持続感染)」です。
妊娠中や産後に悪化することがまれにあります。
感染は主に産道感染ですが、ウイルス量が多いと胎内感染も起こります。
「B型肝炎母子感染防止対策」という厚生労働省の指針に沿ってきちんと対策することが大切です。
なお、配偶者への感染は、HBワクチンを接種することで防げます。
C型肝炎ウイルス
抗体陽性であれば「抗原」検査(ウイルス検査)を行い、それも陽性ならHCVキャリアとします。
赤ちゃんへの感染は10%程度といわれており、感染経路も明確ではありませんが、妊娠中にウイルス量が多くなると、母子感染の確率も高まりますので、内科での妊娠中のフォローが大切です。
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)
日本ではエイズの患者数が少ないため、統計的に偽陽性が多く出ます。
スクリーニング陽性でも実際に感染している可能性は5%以下といわれていますので、追加検査を受けましょう。
もし追加検査で感染が確定すれば、通常はエイズ治療拠点病院での周産期管理となります。
HIVの母子感染は、胎内・産道・母乳のいずれの経路でも感染しますが、妊娠中および産後の速やかな治療により、母児感染の確率を下げることが可能です。
梅毒(梅毒トレポネーマ)
妊婦さんは自覚症状のない潜伏梅毒のケースが多く、陽性者はこのところ増加傾向にあります。
赤ちゃんには胎盤を経由して感染し、胎児死亡や先天梅毒になる確率はとても高いことが知られています。
梅毒は増加傾向にあり、妊娠中に初感染するケースも増えています。
主に性交渉で感染しますが、初期に陰性であっても、その後、感染を疑うようなエピソードがあれば、必ずかかりつけの産科に申し出てください。
風疹ウイルス:📖風疹の記事はこちらから
妊娠初期にスクリーニングとして抗体検査を行います。
抗体価が高い場合は最近の感染を疑いますが、個人差が大きいので高くても問題ないことが多く、むしろ、発熱・発疹・首のリンパの腫れや風疹患者との接触歴がある、小児との接触が多い就労などの方には注意が必要です。
ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)
感染しても一生のうちにATLを発症する確率は5~10%で、9割以上の人は問題なく生涯を終えます。
しかし、発症した場合の有効な治療法は確立しておらず、2年以内にほとんど死亡してしまうため、感染予防が何よりも重要な疾患です。
以前から九州地方に多いとされていますが、人口の移動が多くなった昨今は、九州地方以外でも気をつけなければなりません。
性器クラミジア
妊娠後期までにクラミジア抗原検査を行います。
産道感染により赤ちゃんが新生児クラミジア結膜炎、咽頭炎、肺炎などになるため、分娩までに治療を完了する必要があります。
なお、一旦治療しても、パートナーがクラミジア感染症であった場合は、性交渉により再び性器クラミジアになります(キャッチボール感染)。
つまり、パートナーと同時に治療する必要があります。
B群溶血性レンサ球菌(GBS)
だいたい5~10人に1人が持っている腟内の常在菌で、お母さんにはほぼ無害ですが、分娩時に産道感染することがあります。
赤ちゃんに感染すると治りにくい肺炎や髄膜炎、敗血症などを起こします。
分娩時に有効な抗生剤を投与することで発症の確率を20分の1に減らすことができます。
腟カンジダ症・トリコモナス・淋病
カンジダと淋病については、赤ちゃんに産道感染して、皮膚炎や結膜炎などを起こすことが知られています。
トリコモナスは、産道感染はほとんどありませんが、早産のリスクになる可能性があります。
いずれも胎内感染はしないため、分娩までにきちんと治療すれば問題はありませんが、淋病については抗生剤の効かないスーパー淋病が見つかっています。
とにかく感染機会を無くすことが大切です。
施設によっては妊婦健診で調べることのある感染症
トキソプラズマ
サイトメガロウイルス
感染後は一生を通じてサイトメガロウイルスが体内に潜伏し、体液に排出され、ヒトからヒトへの感染が起こります。
ただし、すでに感染して抗体があれば、通常は再感染しても「感染症」という重い病態になることはありません。
抗体を持たない妊婦さんが初めてサイトメガロウイルスに感染すると、胎盤を経由して赤ちゃんにも感染し、高率で重い「感染症」を引き起こします。症状は多彩で、発育遅延や小頭症、網膜炎、先天性難聴などが出現します。
また、確率は低いですが、抗体があっても妊娠中の再感染や再活性化によって、胎内感染する可能性が1.4%程度あるのが、トキソプラズマや風疹と違う点です。
再活性化を防ぐ方法や確定した治療法はありません。
感染の機会を減らすことが唯一の予防であり、とても大切です。
【参考】TORCH症候群について
TORCH症候群とは、妊娠中の感染により、赤ちゃんに重篤な障害を引き起こすことの多い感染症の頭文字をとって名付けられた概念です。
T:トキソプラズマ
O:othersその他(梅毒、B型肝炎、水痘、パルボウイルスB19など)
R:Rubella風疹
C:サイトメガロ
H:ヘルペス
日本ではサイトメガロウイルスとトキソプラズマの頻度が高いです。
トーチの会という患者会があり、妊婦さんの感染症に対する啓蒙活動を行っています。
疑わしい症状が出たら調べる感染症
ヘルペス
赤ちゃんは主に産道感染ですが、頻度は少ないものの胎内感染もあり重症になります。
外陰ヘルペスの場合、初めての感染かどうかや治療が進んでいるかどうかで帝王切開を選択するケースもあります。
新生児ヘルペスは単純な発疹で済むこともありますが、中枢神経や全身に波及するものは予後不良で死亡することもあります。
有効な抗ウイルス剤があり、速やかな治療が大切です。
尖圭コンジローマ
HPVは子宮頸がんの原因ウイルスですが、がん化するものとは型が異なります。
赤ちゃんには産道感染して喉などにイボができることがありますが、多発していなければ、経腟分娩でも問題ないという考えが主流です。
なお、子宮頸がんワクチンによる尖圭コンジローマの予防効果は非常に高いですが、日本では無料にもかかわらず、ほとんど施行できていないのが現状です。
2022年1月時点では、小学校6年生から高校1年生までの女子が公費助成の対象です。
また、1997~2005年度生まれの女性は、打ち控えへの救済措置として2022年4月から2025年3月までの3年間助成対象になることが決まっています。
水痘(すいとう):📖水疱瘡の記事はこちらから
発熱とかゆみを伴う全身の発疹が特徴です。
多くの人が抗体を持っていますが、抗体を持たない妊婦さんが初めて感染すると、胎内感染して赤ちゃんに先天性水痘症候群(四肢低形成、小眼球症、網脈絡膜炎、小頭症など)を来すことがあります。
ただし、風疹と比べると母子感染の確率は低く、最もリスクのある時期でも1.4%程度と考えられています。
むしろ、お母さん自身の水痘感染が重症化しやすいので、速やかな抗ウイルス剤による治療が必要です。
なお、帯状疱疹はウイルスの再感染・再活性化ですが、胎児には感染しません。
伝染性紅斑(リンゴ病):📖りんご病の記事はこちらから
パルボウイルスB19の飛沫・接触感染によって起こります。
お母さんが妊娠中に初めて感染した場合、17~33%の確率で胎内感染します。
胎児貧血や全身がむくむ胎児水腫を起こす危険があり、重症化すると生命に関わります。
治療法もワクチンもないため、マスクや手洗いで感染しないようにするのが大切です。
リステリア症
起こる確率は低いのですが、重症になると致死率が20~30%と非常に高いです。
また、リステリアは胎内感染することが知られており、流産や死産の確率が2割、分娩後に新生児リステリア症となる確率が6割以上という報告もあります。
リステリア菌はどこにでも存在する菌であり、健康な人であれば少量を摂取してもリステリア感染症になることはありません。
しかし、妊婦さんはハイリスクになります。
日本での集団発生は少ない(調査方法の差という意見もあります)のですが、海外では生ハムやサラミ、スモークサーモン、チーズ、サラダ、最近では、メロンによって集団発生が報告されています。
つまり、加熱せずに食べられるものが食中毒の原因となります。
海外から食品を取り寄せるケースも増えているようですが、食べるなら必ず加熱、そして加熱しないものは避けた方がよいでしょう。
麻疹:📖はしかの記事はこちらから
発熱の後、頬の内側に特有の発疹が出ます。
その後、全身に発疹が出て高熱になります。
有効な治療法はなく、安静と脱水に注意するくらいです。
風疹と違い、胎内感染はしないと考えられていますが、高熱や体調の悪化により流早産のリスクは高まります。
麻疹ワクチンは予防に非常に有効ですが、妊娠中には打てません。
また抗体の量が10年くらいで減少するため海外では再接種しますが、日本では行っていません。
新型コロナウイルスやインフルエンザには徹底した感染予防を
新型コロナウイルスに感染したときの初期症状は、発熱、せき、だるさなど、いわゆる風邪症状の他、頭痛や下痢、においや味が分からなくなるなどが一般的です。
ほとんどの人は軽症のまま回復しますが、重症化すると肺炎を起こしたり、さまざまな臓器に悪影響を及ぼしたりして死に至ることもあります。
現時点では、お母さんが妊娠中に感染しても、赤ちゃんへの影響は非常に低いとされていますが、妊娠中は免疫力が低下しているので、お母さんが重症化しやすいリスクがあります。
ワクチンを接種した場合でも油断せず、日頃の感染症対策を徹底しましょう。
妊娠中にインフルエンザに感染しても胎内感染はしませんが、重症になって高熱が続くと、流産や早産の可能性が高まることも考えられます。ワクチンを接種して、重症化する確率を減らしましょう。
▶参考:「新型コロナウイルス感染症対策~妊婦の方々へ~」厚生労働省
(2022年1月閲覧:https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000630978.pdf)
感染症を予防するために生活習慣に気を付けよう
●人混みを避ける
混雑した電車や繁華街など、人が密集する場所はできるだけ避け、飛沫感染を予防するため、会話をする際も相手との距離を取るようにします。
●手洗いやうがいをこまめにする
帰宅後や食事の前には、手洗いとうがいを忘れずに行い、調理の前後にも手洗いをします。
≪正しい手の洗い方≫
(2022年1月閲覧:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf)
※手洗いの前に爪は短く切っておく。時計や指輪は外す。
①流水でよく手をぬらした後、石けんをつけ、手のひらをよくこする。
②手の甲を伸ばすようにこする。
③指先・爪の間を念入りにこする。
④指の間を洗う。
⑤親指と手のひらをねじり洗いする。
⑥手首を洗う。
●外出時はマスクを着用する
最も予防効果が高いのは不織布マスクです。マスクと皮膚の間に隙間ができないように正しく着用します。
●家族そろって感染症対策をする
感染症は家族から感染することが少なくありません。一緒に住む家族もしっかりと感染症対策を行いましょう。
《 監修 》
-
井畑 穰(いはた ゆたか) 産婦人科医
よしかた産婦人科診療部長。日本産婦人科学会専門医、婦人科腫瘍専門医。東北大学卒業。横浜市立大学附属病院、神奈川県立がんセンター、横浜市立大学附属総合周産期母子医療センター、横浜労災病院などを経て現職。常に丁寧で真摯な診察を目指している。
▶HP https://www.yoshikata.or.jp/ よしかた産婦人科
【本サイトの記事について】
本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます. Unauthorized copying prohibited.



 妊娠~産後記事を検索
妊娠~産後記事を検索