【医師監修】伝染性軟属腫( 水いぼ /MCV)はどんな病気?治療方法は?
2024.07.08
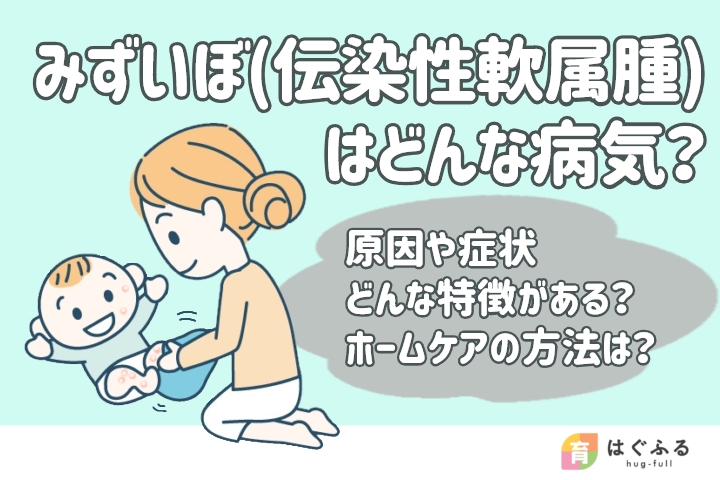
目次
1. 伝染性軟属腫(水いぼ/MCV)とはこんな病気【監修】松井 潔(まつい きよし) 総合診療科医
症状:いぼ
体の部位:全身
伝染性軟属腫は、皮膚のウイルス感染症の一つです。
伝染性軟属腫ウイルスに接触感染することで皮膚に「いぼ」ができます。
みずみずしい光沢があることから「水いぼ」と呼ばれています。
他の部位に次々とできるのが特徴です。
特に乳児やアトピー性皮膚炎の子どもは、皮膚のバリア機能が未熟なために感染しやすいとされます。
ステロイドを塗ると水いぼが増加してしまい、アトピー性皮膚炎の治療が適切にできなくなってしまうため注意が必要です。
多くの子どもでは、6カ月~3年で自然治癒が期待できますが、個人差が大きくその患児がいつ治るかを予測することは困難です1,2,3) 。
確実な治療法として、医師がピンセットでつまみ取る方法(摘除=てきじょ)があります。
2. 伝染性軟属腫(水いぼ)の原因
原因は、伝染性軟属腫ウイルスです。
接触感染によって皮膚にウイルスが侵入し、表皮組織を変性させます。
それにより、いぼができます。
みずみずしい光沢があることから水いぼと呼ばれますが、いぼの中身は水ではなく白い粥状のものです。
ウイルスや変性した皮膚などから成り、「モルスクム小体」と呼ばれます。

7歳以下の子どもに多い病気です1) 。
熊本県の皮膚科診療所が行った調査では、年齢のピークは3歳でした2) 。
初夏~夏に多く発症します2,3) 。
3. 伝染性軟属腫(水いぼ)の症状
水いぼは、皮膚の色と同じかやや赤みがかっています。
小さいもので直径1㎜くらい、大きいもので直径5㎜くらいです3) 。
症状はないか、あっても軽いかゆみです。
水いぼが1個できると、その近くの他の部位にいくつもできてくるのがよくあるパターンです。
接触感染しますので、水いぼを引っかいた手で、「他の部位に触り、自分でウイルスを付けてしまう」といったイメージです。
症状が出やすい部位は顔面、脇の下、肘前部、胴体、膝の後ろのくぼみ、下腿部(膝から足首までの部分)が最もよく発症する部位です。
手のひら、足の裏、頭皮は発症しません。
潜伏期間は約2~7週間です。
なお、免疫力の低下、アトピー性皮膚炎、または皮膚の損傷を受けた子どもたちは、より広範囲に感染が広がる傾向があります。
皮膚と皮膚との接触、ウイルスのついた物(タオル、バススポンジ、水着、ビート板、浮き輪など)の共用によって感染しますので、他の子どもにもうつすリスクがあります1) 。
![]()
💡水いぼの特徴まとめ💡
・7歳以下の子どもに多い病気
・初夏~夏に多く発症
・接触感染のため、水を介して感染しない
・皮膚と皮膚との接触、ウイルスのついた物の共有を避ける
・皮膚の色と同じかやや赤みがかっている
・軽いかゆみがある場合がある
・直径1~5㎜ほどの丘疹
![]()
4. 伝染性軟属腫(水いぼ)の検査でわかること
医師が皮膚症状を診て水いぼかを判断します。
見た目で診断がつきにくい時は、「治療的診断」といって、まずいぼを摘除をし、内容物を観察して診断することもあります3) 。
5. 伝染性軟属腫(水いぼ)の治療法と薬
治療は、先端がリング状になった特殊なピンセットで水いぼの内容物を摘除することです。
他に、ヨクイニンエキスの飲み薬が使われることもあります。
摘除は多少なりとも痛みがあり、子どもの年齢や水いぼの数によっては耐えられないこともあります。
そのため、摘除について医師の間でも意見が分かれています1,2) 。
摘除しないほうがよいとする考えは「痛い思いをさせなくても、自然に治るのだから経過観察でよい」ということです。
一方、摘除したほうがよいという考えは「他の場所に広がったり、他の子にうつしたりする可能性があるから、早いうちに治しておいた方がよい。数が増えてからの摘除では、かえって本人はつらいのではないか」というものです。
それぞれの医師が単純にどちら側かに分かれるのではなく、その子の皮膚の状態や生活の状況に応じて適切な方法が提案されることでしょう。
それをもとに、どうするかを考えてみましょう。

たとえば、大部分の水いぼは、6~9カ月で自然に消えるとされますが、2~3年続くこともあります1,3) 。
子どもの水いぼが、どのくらいの期間で消えるかは予測しづらいといえます。
先に紹介した熊本の研究によると、摘除では約半数が1回の治療で完了し、再発・再感染した場合でも多くの患者さんが初回治療から3カ月の間に治癒しました2) 。
なお、治療の大きな課題である「摘除時の痛み」の対応については、前もって局所麻酔のパッチ剤を貼っておくことができます。
自宅で貼ってから医療機関に向かったり、院内で医療者に貼ってもらったりします。
貼ってから1時間くらい経つと麻酔が効いてくるので、摘除時には痛みを感じにくくなります4) 。
ただし、全員にではありませんが、貼った部位の赤み・かゆみなどの副作用があるため、麻酔薬にアレルギーがある人には使えません。
6. 伝染性軟属腫(水いぼ)の予防とホームケア
予防は、皮膚のバリア機能を保っておくことです1) 。
皮膚の汚れをきちんと落とした後で、保湿剤を塗るのがよいでしょう(📖保湿薬 ・皮膚保護薬)。
アトピー性皮膚炎の炎症はしっかりと抑えておきましょう(📖アトピー性皮膚炎)。
水いぼができたら、触らないようにしましょう。
タオルなどの共用を避けましょう。
Q プールやお風呂では感染しますか?
水を介して感染はしません。
ただしビート板や浮き輪、タオルを介してうつる可能性はあるため、共用は避けます。1)
プールの後はシャワーで肌をきれいに洗いましょう。
プールの後は、皮膚が乾燥しないように、保湿をしておきましょう。
Q 伝染性軟属腫(水いぼ)になった場合保育園や幼稚園はいつからいけるの?1)
この疾患のために、保育園や幼稚園を休む必要はありませんが、プールなどの肌の触れ合う場ではタオルや水着、ビート板や浮き輪の共用を控えるなどの配慮が必要です。
国で定められたルールはないため、園に対応を確認しましょう。
『参考資料』
1) 日本小児皮膚科学会.みずいぼ.(2024年2月閲覧: http://jspd.umin.jp/qa/01_mizuibo.html)
2) 横山眞爲子ほか.日臨皮会誌 32:574-579,2015
3) 岩月啓氏監修.標準皮膚科学第11版.医学書院 2020
4) くすりのしおり.ペンレステープ18mg (2024年2月閲覧: https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=13859)
会員サイトページにて、水いぼ体験談記事掲載中
《 監修 》
-
松井 潔(まつい きよし) 総合診療科医
神奈川県立こども医療センター総合診療科部長。愛媛大学卒業。
神奈川県立こども医療センタージュニアレジデント、国立精神・神経センター小児神経科レジデント、神川県立こども医療センター周産期医療部・新生児科等を経て2005年より現職。
小児科専門医、小児神経専門医。
松井潔先生監修記事一覧
📖子育てに掲載中の記事
【本サイトの記事について】
本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます. Unauthorized copying prohibited.



 子育ての記事を検索
子育ての記事を検索
