臍帯血 (さいたいけつ)とは?お母さんと赤ちゃんをつなぐ「へその緒」を通る血液【医師監修】
2025.08.06
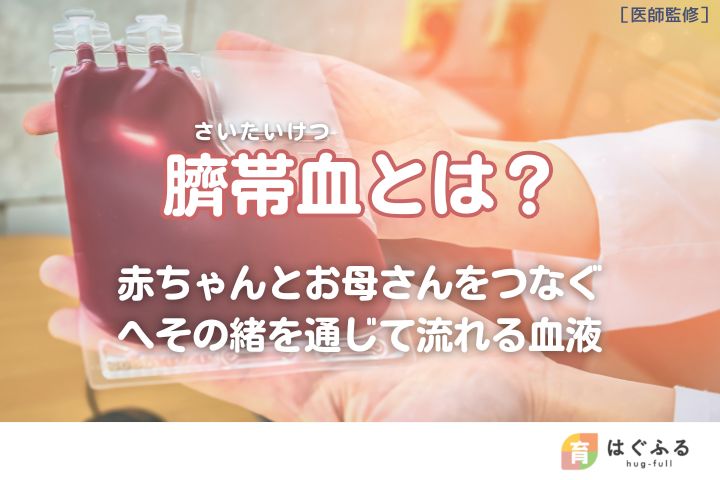
目次
1:臍帯血(さいたいけつ)とは?
臍帯血という言葉を聞いたことがありますか。
臍帯とは、お母さんと赤ちゃんをつなぐ「へその緒」のことです。
お母さんの子宮に集まった動脈の血液は、胎盤を経由し、へその緒を通って赤ちゃんに供給され、再び血液はへその緒を通って胎盤に戻ります。
このへその緒(臍帯)を通る血液を臍帯血と呼びます。
赤ちゃんが生まれた後に臍帯を切断しますので、臍帯血はそのまま出産時に失われます。
ところが、臍帯血には「造血幹細胞(ぞうけつかんさいぼう)」という細胞が豊富に含まれていることがわかり、破棄せずに臍帯血を利用することの研究が30年以上前からなされてきました。
2:臍帯血移植と骨髄移植
造血幹細胞は、通常は骨髄の中にあり、赤血球や白血球、血小板などの血液細胞を造る「血を造る元となる細胞」です。
白血病などの血液の病気の中には、造血幹細胞の異常でおこるものがありますが、骨髄移植が極めて有効な治療法とされています。
しかし骨髄移植は患者さんの身体的負担が非常に大きく、白血球の型(HLA)が完全に一致しないと移植ができません。
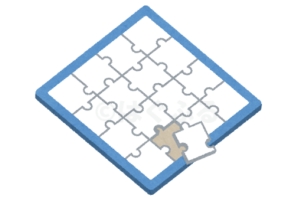
今すぐに移植が必要であってもHLAが完全に一致する骨髄細胞が得られないかもしれないのです。
最も一致する可能性の高い兄弟姉妹であっても4分の1、他人であれば数万分の1ともいわれています。
骨髄移植が必要な側から見ると、最終的に骨髄移植ができる人は全体の3分の1くらいしかいません。
たったの3分の1です。残りの3分の2は適合する骨髄が間に合わず、お亡くなりになられているのが辛い現状です。
ところが、「臍帯血」から得られる造血幹細胞であれば、骨髄移植と違って完全にHLAが一致しなくても使用でき、移植できる可能性がとても高いことがわかってきました。
3:骨髄移植と臍帯血移植の実際
骨髄バンクという言葉はどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。
これは自分の白血球の型(HLA)を前もって届けておくシステムです。
届けておいたHLAと一致した患者さんが見つかったとき、提供する人(ドナー)として骨髄を採取させていただくことになります。
ただし、移植は非常に大変で、まず、移植を受ける側の患者さんの免疫システムをほぼゼロにしないと移植ができないため、数日前から無菌室に入って抗がん剤や放射線照射などを行います。
十分に免疫抑制と無菌化が行われたタイミングに合わせ、ドナーに入院していただき骨髄を採取し、速やかに点滴投与します。
移植した骨髄が生着※し、新しい血液が造り出されるまでは通常1カ月以上かかり、その間はずっと無菌室にいなければなりません。
本当に辛い治療になるのですが、現在の医学では骨髄移植以上の治療法はなく、うまく生着すればほぼ健常な人と同じ生活を送れるようになります。
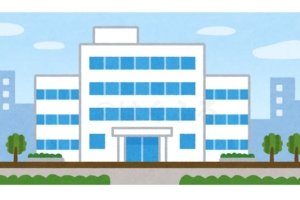
※生着…提供を受けた造血幹細胞が、患者さんの骨髄の中で血液を作り始めること
骨髄を提供するドナーにとっても、骨髄採取は決して楽な処置ではなく、仕事などとの兼ね合いも含めて相当の負担になるのも事実です。
それでも命を救うために快く骨髄バンクに登録していただいている方々には感謝しかありません。
骨髄バンクに登録している方の中で、実際にドナーになれるのは5%以下で、多くは一致することなく55歳の年齢制限を超えてしまいます。
それくらいHLAが一致するドナーは見つかりにくいのです。
ところが、「臍帯血」の造血幹細胞を移植する「臍帯血移植」の場合、骨髄移植と異なりHLAが完全に一致する必要がなく、適合した臍帯血が見つかる可能性が高くなります。
また、臍帯血移植は、あらかじめ採取して保存されているものを使うので、移植に際してドナーの負担や都合がないことも大きなメリットです。
ただ、デメリットもあり、骨髄移植より生着率が低いことが知られていますし、感染症になる確率も高いとされています。
また臍帯血では量が少ないため、HLAが一致しても必要な患者さんの体格によっては十分な量が確保できない可能性もあります。
4:臍帯血バンクとは?
現在国内では、年間1,000件を超える臍帯血移植が、公的臍帯血バンクを通じて実施されています。
公的臍帯血バンクは、分娩時に採取され、提供された臍帯血を適正な状態で保存し、臍帯血移植が必要な患者さんが移植をする際に、移植を行う医療機関に渡します。
臍帯血の提供は無償で、使用の対象は本人や家族を優先できず、対象者の指定もできません。
▼臍帯血供給事業者として厚生労働大臣の許可を受けている公的臍帯血バンクは、全国で以下の6カ所です(2025年1月現在)。
・日本赤十字社 関東甲信越さい帯血バンク
・一般社団法人 中部さい帯血バンク
・日本赤十字社 近畿さい帯血バンク
・特定非営利活動法人 兵庫さい帯血バンク
・日本赤十字社 九州さい帯血バンク
5:民間の臍帯血バンクについて
臍帯血バンクには、民間の臍帯血バンク(臍帯血プライベートバンク)もあります。
こちらはボランティアではなく、自分や家族のために有償で臍帯血を保存するビジネスです。
将来本人や家族が病気になったときや、医学としてはまだ確立されていない再生医療などに利用する場合、もしも自前の臍帯血がバンクにあれば移植における最大の問題(HLAの一致)がほぼ解決します。
ただし、民間の臍帯血バンクは厚生労働大臣の管理下にない組織のため、臍帯血の調整や保存などがきちんとした基準で行われているかどうかの調査監督などありませんし、民間企業ですので倒産や売却などの可能性もあり、その場合の対応についても明確なルールはありません。
以前に、経営破綻した民間臍帯血バンクから違法に流出した臍帯血が美容外科などに販売され、アンチエイジングなどに使用された事件がありました。
臍帯血を預けた人にとっては、高額の保管費用を払って何も得られなかったことになります。
また、保管期間は一般に10年とされており、10歳までに使わなければ、それ以降に必要になったとしても使用できないことになります。
6:臍帯血を提供するには
公的臍帯血バンクの場合、臍帯血を提供できるのは、公的臍帯血バンクと提携している産科医療機関で出産した場合のみです。
どの医療機関が該当するかは、日本赤十字社の「造血幹細胞移植情報サービス」のホームページで確認することができます。
施設数は多くありません。
また提携施設であっても分娩のタイミングや状況によっては提供できないこともあるようです。
7:臍帯血の採取方法
赤ちゃんを出産時、へその緒を鉗子などで止めて(結紮)臍帯切断します。
そして速やかに胎盤側の臍帯の血管に針をさして採取するという手順になります。
早ければ早いほど多くの臍帯血が取れます。
ところが、へその緒を結紮して切るタイミングについては様々な意見があります。
アメリカのガイドラインでは、正期産か早産かにかかわらず、原則として出生してから30-60秒は結紮を遅らせたほうが良いということになっています。
しかし、遅らせすぎるのはリスクが高まるという研究もあります。
日本ではそれらのことを踏まえて、結紮を60秒程度遅らせたほうが良いとしています(CoSTR2024より:すぐに蘇生や呼吸補助をしたほうが良いケースもありますので状況に応じて対応することになります)。
臍帯血は、臍帯切断してから胎盤娩出までに採取しますので、結紮の遅延を行うと臍帯血の採取量が減ります。
したがって臍帯血を取ることを優先するならば遅延せずに速やかに結紮切断を行わなければなりません。
切断そのものは赤ちゃんやお母さんに一切痛みはありません。
赤ちゃんに関しても早産例を除けばおおむね不利はないと考えますが、お母さんに関しては分娩後の処置が若干遅れるため、分娩時出血が増加してしまう可能性があります。
採取した臍帯血は公的臍帯血バンクに送られ保存されます。
また、感染症や細菌の検査、血液型や白血球の型の判定などを行い、移植可能と判断されれば採取後4カ月くらいたった頃にお母さんと赤ちゃんの健康状態を確認する書類が届きます。

返送した書類に問題なければ、提供した臍帯血は公的臍帯血バンクに登録され、医療機関からの要請に応じて移植のために該当の病院に届けられます。
公的な臍帯血バンクでは、臍帯血の提供は献血と同様で無償です。
分娩時の状況により予定していた採取を取りやめても不利益はありませんし、採取後でも断ることができます。
もちろん、提供した臍帯血が移植され、その結果がもしも好ましくない場合でも、提供者は一切の責任を問われません。
公的臍帯血バンクへの臍帯血の提供は、赤ちゃんの生まれて初めてのボランティアと言われています。
たくさんの臍帯血が集まることは、臍帯血移植により救える命が増えることです。
もし、公的臍帯血バンクに少しでもでも興味があれば、臍帯血の提供について検討してみてはどうでしょうか。

一方、民間の臍帯血バンクは有償であり、臍帯血の保存のために毎月2000-5000円くらいが必要なようです。
維持費が上昇する可能性や、企業が破綻した場合の保証はありません。
しかし、民間の臍帯血バンク以外に「自身の赤ちゃんや家族のため」に臍帯血を保存する方法はなく、しかも自分の造血幹細胞という唯一無二の極めて貴重な血液を使える可能性を得るわけですから、そのための費用としては格安だとも感じます。
また採取可能な施設の数も公的臍帯血バンクにくらべると多いです。
![]()
今回は、臍帯血に関わる様々な状況をお話しました。
単純に良い悪いで決められないことも多いので簡単ではありませんが、臍帯血の活用と未来については無視できないものでもあります。公的バンクも私的バンクもそれぞれに大切な役割を担っています。大切な臍帯血が有効に活用されるようご検討ください。
《 監修 》
-
井畑 穰(いはた ゆたか) 産婦人科医
よしかた産婦人科診療部長。日本産婦人科学会専門医、婦人科腫瘍専門医。東北大学卒業。横浜市立大学附属病院、神奈川県立がんセンター、横浜市立大学附属総合周産期母子医療センター、横浜労災病院などを経て現職。常に丁寧で真摯な診察を目指している。
▶HP https://www.yoshikata.or.jp/ よしかた産婦人科
【本サイトの記事について】
本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます。 Unauthorized copying prohibited.
登場する固有名詞や特定の事例は、実在する人物、企業、団体とは関係ありません。インタビュー記事は取材に基づき作成しています。
また、記事本文に記載のある製品名や固有名詞(他企業が持つ一部の商標)については、(®、™)の表示がない場合がありますので、その点をご理解ください。



 妊娠~産後記事を検索
妊娠~産後記事を検索