育児中のテレワーク(在宅勤務)は認められているの?【社労士監修】(2025年3月作成版)
2025.05.15
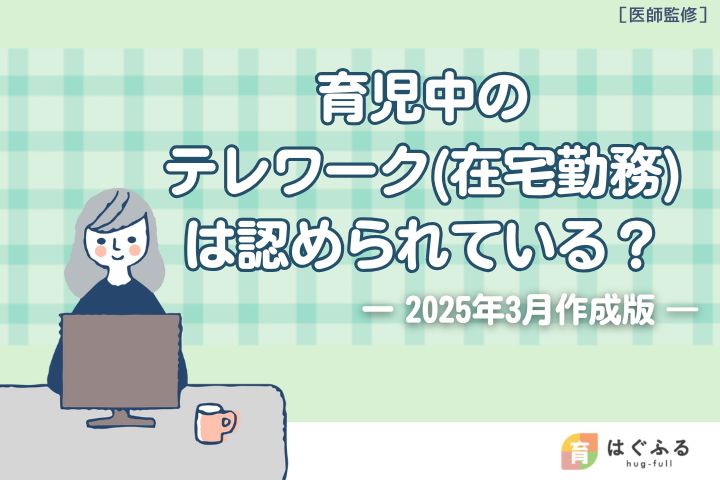
【監修】木幡 徹(こはた とおる) 社会保険労務士
通勤に時間を取られないテレワークを求める声が、育児中の方から特に高まっています。
今回の記事では育児中のテレワークの法律的な扱いについて、ご案内をいたします。
育児中のテレワーク勤務を直接義務付ける法律はない
まず、育児中の方がテレワークを希望した場合、会社が必ず認めなくてはいけないという法律はありません。
テレワーク希望が認められるかは、あくまで会社が定めたルール次第ということになります。
しかしながら、直接的ではないですが、ゆるやかにテレワークを促す規定が育児介護休業法にあります。
育児介護休業法では、3歳未満の子どもがいる方に対して、労働時間の制限以外にも、一定の配慮を行うことを努力義務として課しています。
一定の措置とは、下記のとおりです。

2025年4月1日から在宅勤務等(テレワーク)が上記の措置に追加され、これまで以上に会社に対して理解を促す傾向が鮮明になりました。
とはいえ、あくまで「努力義務」ですから、会社が上記の措置を絶対に行わなくてはならないということではありません。
上記の措置を導入していない会社へ、行政が指導や罰則を科すこともありません。
会社に対して要望を上げることはもちろん問題ありませんが、強気に出すぎるのは控えた方がいいでしょう。
【産休・育休明け】子育て中の勤務時間はどうする?「 時短勤務 」について【社労士監修】
3歳以上小学校入学前の子どもがいる方への配慮措置は義務化へ!
一方、 3歳以上小学校入学前の子どもがいる方へは、2025年10月より一定の措置が義務付けられます。
会社は下記の中から2つ以上の措置を行う必要があります。
・フレックスタイム制もしくは始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・テレワーク等(月10日以上)
・新たな休暇の付与(養育両立支援休暇の付与)
・短時間勤務制度
・保育施設の設定運営その他これに準ずる便宜の供与
対象の子どもがいる従業員は、上記のうち会社が講ずる2つ以上の措置から1つの措置を選択することができます。
こちらは努力義務ではなく必ず行わなくてはいけない措置ですが、上記の中から2つの措置を選択するのは会社ですので、自身の勤務先が必ずテレワークを導入するとは限りません。
しかしながら、コロナ禍等でテレワークを一部でも実施した会社であれば、導入のハードルはさほど高くないと考えられますし、導入機運を高めることになるのは間違いないでしょう。

なお、労使協定の締結により、下記の方は対象外となることがあります。
・1週間の所定労働日数が2日以下の方
・業務の性質または業務の実施体制に照らして、1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する方(休暇の時間単位での取得の場合に限ります)
このように、育児中であれば確実にテレワークができるという法律にはなっていません。
業務の性質上テレワークが困難なケースも多いですし、物理的に実施可能であっても業務の質やパフォーマンスへの懸念を抱く会社も多く、将来に向かっても義務化はなかなかハードルが高いでしょう。
保育園の送り迎えなどでテレワークが必要になる場合などは、元々テレワークに寛容な会社へ転職することや、時短勤務でなんとか乗り切るなどの解決方法が必要になってくるかもしれません。

《 監修 》
-
木幡 徹(こはた とおる) 社会保険労務士
1983年北海道生まれ。大企業向け社労士法人で外部専門家として培った知見を活かし、就業規則整備・人事制度構築・労務手続きフロー確立など、労務管理全般を組織内から整える。スタートアップ企業の体制構築やIPO準備のサポートを主力とし、企業側・労働者側のどちらにも偏らない分析とアドバイスを行う。
▶HP https://fe-labor-research.com/【本サイトの記事について】
本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます。 Unauthorized copying prohibited.
登場する固有名詞や特定の事例は、実在する人物、企業、団体とは関係ありません。インタビュー記事は取材に基づき作成しています。
また、記事本文に記載のある製品名や固有名詞(他企業が持つ一部の商標)については、(®、™)の表示がない場合がありますので、その点をご理解ください。



 妊娠~産後記事を検索
妊娠~産後記事を検索