『 日本脳炎 』とはどんな病気?原因や症状、予防方法は?【医師監修】
2025.08.14
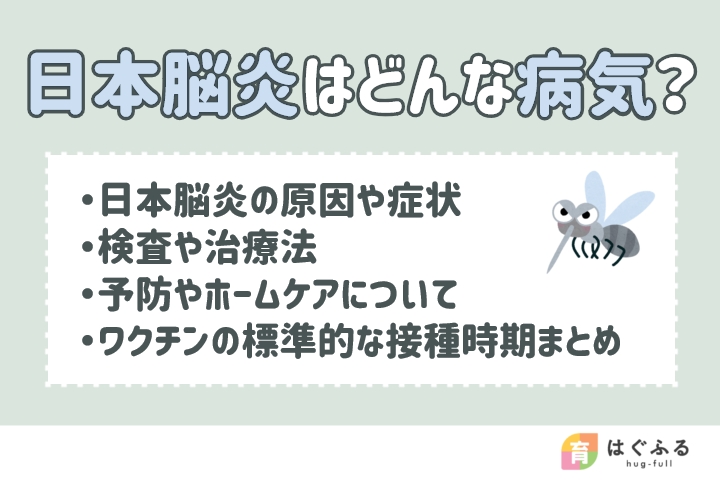
1. 日本脳炎とはこんな病気
症状別:発熱、頭痛、意識障害、けいれんなど
体の部位:全身
日本脳炎とは、日本脳炎ウイルスの感染によって引き起こされる急性の脳炎です。
日本に多いから日本脳炎という名前がついているわけではありません。
日本脳炎は1920年代から様々な研究が行われ、研究をしていた先駆者が日本人だったために、「日本脳炎」と名付けられました。
1930年代には、林道倫・笠原四郎らの手により、当時日本で流行っていた奇病がウイルスによる脳炎が原因だと発見され、日本脳炎ウイルスが相次いで患者から分離されました1) 。
日本脳炎は、日本、韓国、中国、台湾、フィリピン、インドネシア諸島など、アジアに広くみられる病気です。
世界で毎年1万人が命を落としているとされます2) 。
日本脳炎ウイルスはブタの体内で増え、そのブタの血を吸った蚊が人を刺した時に感染します。
したがって、豚のいない地域では感染はまれです。

日本では1960年前半までは年間1,000人以上の日本脳炎患者が発生しており、当時の患者の多くは小児や高齢者でした2) 。
ワクチンが開発されてから患者は激減しましたが、今なお平均して年間5例程度は発生しています3) 。
2. 日本脳炎の原因
原因は、日本脳炎ウイルスです。
水田と養豚場があると発生する蚊(主にコガタアカイエカ)が、たまたま人の血を吸った時にウイルスを感染させます。
蚊はどこからウイルスをもらうのかというと、ブタなどの動物です。
日本脳炎ウイルスに感染したブタは4~5日間、血液中のウイルス量が高いレベルで推移しています4)。
そのブタを蚊が刺して吸血した時にウイルスも一緒に吸い、それを保持した状態で人を刺すと人に感染するというわけです。
ウイルスは人の皮膚に侵入したのち、内臓に感染し、脳にも移行します。ただし、人から人への感染はありません5)。
3. 日本脳炎の症状
感染しても大半の人は症状がありませんが、1,000人に1人程度は日本脳炎を発症します6) 。
6~16日間の潜伏期間を経て、38~40℃またはそれ以上の急な発熱、頭痛、呼吸不全、吐き気・嘔吐、めまいなどを発症します5) 。
その後、意識障害、麻痺、けいれんといった症状が現れます。
20~40%の患者は命を落とすとされ、特に子どもや高齢者はそのリスクが高まります6) 。
救命できても、45~75%の患者はけいれん、麻痺など神経系の後遺症があります6) 。
4. 日本脳炎の検査でわかること
急性期の血液検査で日本脳炎ウイルスの遺伝子やウイルスに対する抗体の有無を調べます3) 。
ウイルスは脳に移行するため、髄液(脳と脊髄を循環する液体)からウイルス遺伝子や抗体が検出されることもあります3) 。
発症後1週間以降の回復期に血液中の抗体価が急性期の4倍以上に上昇していれば、感染はほぼ確実です5) 。
また、血液検査で白血球数が軽度に上昇します。
尿検査では、急性期に無菌性の膿尿、(顕微鏡レベルの)血尿、蛋白尿などがみられることがあります5)。
5. 日本脳炎の治療法と薬
日本脳炎に特化した抗ウイルス薬はなく、予防が重要となります。
治療は高熱やけいれんなどに対する対症療法が中心となります。
6. 日本脳炎の予防とホームケア
日本脳炎はワクチンで予防できる病気の一つです。
ワクチンは大きく分けて「生ワクチン」と「不活化ワクチン」があります。
日本で使われている日本脳炎ワクチンは「不活化ワクチン」です。
ウイルスをホルマリンで不活化、つまり感染性を失わせた「不活化ワクチン」が使われ、通常、3歳から4歳にかけて所定の間隔で計3回接種した後、9歳から10歳の間に追加で1回接種するスケジュールです6) 。
ワクチン接種によって、日本脳炎にかかるリスクを75~95%減らすことができます6) 。
副反応として発熱、せき、鼻水、注射部位の紅斑・腫れ、発疹などが現れることがあり、ほとんどは接種3日後までに発現しています6) 。
重大な副反応としては、ごくまれにショック、アナフィラキシー様症状、急性散在性脳脊髄炎(ADEM * )、脳症、けいれん、急性血小板減少性紫斑病などがみられることがあります。
ADEMとは、ワクチン接種後数日から2週間程度で発熱、頭痛、けいれん、運動障害などの症状が現れる病気です6) 。感染症にかかった後に起こることもあるといわれています。
7. ワクチンについて
現在、国内で製造販売され、使用されているワクチン6)
「ジェービックV」
2009年2月23日付けで薬事法上の承認を受け、2009年6月2日から供給が開始
「エンセバック皮下注用」
2011年1月17日付けで薬事承認を受け、2011年4月から供給が開始

世界的には、2008~2009 年に、組織培養ベースの日本脳炎ワクチン (Ixiaro®) がヨーロッパ、オーストラリア、米国で認可され流通しています。
国内でブタに日本脳炎ウイルスがまん延しているかを「抗体保有率」で見ると、地域によっては50%以上や80%以上と報告(=ウイルス陽性の蚊がいると間接的に示唆)されており、注意が必要です7) 。
そこで、ワクチン接種とともに蚊への対策も重要です。
日本脳炎ウイルスの運び屋として重要なコガタアカイエカは、水田のような比較的大きなたまり水で繁殖します。
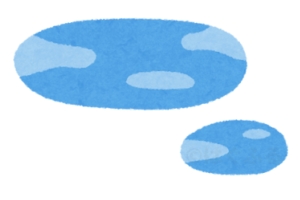
厚生労働省は、蚊に対して次のような予防策を挙げています6) 。
![]()
・夏季、なるべく夜間の外出を控える。
・戸外へ出かける必要があるときは、できる限り長袖・長ズボンを身につける。
・露出している皮膚へ虫除けスプレーなどを使用する。
・蚊が屋内に侵入しないように網戸を使用する。
・夜間の窓や戸の開閉を少なくする。
・蚊帳(かや)を利用する。
![]()
==================
●日本脳炎ワクチンの標準的な接種時期まとめ6)
1期接種:初回接種については3~4歳の期間に6~28日までの間隔をおいて2回、追加接種については2回目の接種を行ってから概ね1年を経過した時期に1回の接種を行います。
2期接種:9~10歳までの期間に1回の接種を行います。
==================
「参考資料」
1. 神奈川県衛生研究所.ウイルス学エピソード(6)ウイルスの命名は誰がする?規則はある?
(2024年12月閲覧:https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken/index.html)
2. 髙崎智彦.ファルマシア 57:366-370,2021.
3. 前木孝洋.Neuroinfection 27:115-123,2022
4. 国立感染症研究所.病原微生物検出情報月報 38巻8号.2017年8月.
5. 国立感染症研究所.感染症週報 第4巻第1・2合併号.2002年1月25日.
6. 厚生労働省ウェブサイト.日本脳炎ワクチン
(2024年11月閲覧:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/japanese-encephalitis/index.html)
7. 国立感染症研究所.ブタの日本脳炎抗体保有状況-2024年度速報第11報-(2024年10月28日閲覧:https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/12961-je-yosoku-rapid2023-11.html)
《 監修 》
-
松井 潔(まつい きよし) 総合診療科医
医療法人産育会 堀病院。
愛媛大学卒業。
神奈川県立こども医療センタージュニアレジデント、国立精神・神経センター小児神経科レジデント、神川県立こども医療センター周産期医療部・新生児科、総合診療科部長等を経て2025年より現職。小児科専門医、小児神経専門医、新生児専門医。
📖子育てに掲載中の松井潔先生監修記事一覧
休日・夜間の子どもの症状で困った時は【☎♯8000】保護者の方が、休日・夜間の子どもの症状にどのように対処したらよいのか、病院を受診した方がよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師に電話で相談できるものです。
この事業は全国統一の短縮番号♯8000をプッシュすることにより、お住いの都道府県の相談窓口に自動転送され、小児科医師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられます。
厚生労働省ホームページ:子ども医療電話相談事業(♯8000)について【本サイトの記事について】
本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます。 Unauthorized copying prohibited.
登場する固有名詞や特定の事例は、実在する人物、企業、団体とは関係ありません。インタビュー記事は取材に基づき作成しています。
また、記事本文に記載のある製品名や固有名詞(他企業が持つ一部の商標)については、(®、™)の表示がない場合がありますので、その点をご理解ください。



 子育ての記事を検索
子育ての記事を検索