不妊治療 の月経周期に合わせた検査( 血液検査・超音波検査・子宮卵管の検査・フーナーテスト)【医師監修】
2021.04.27
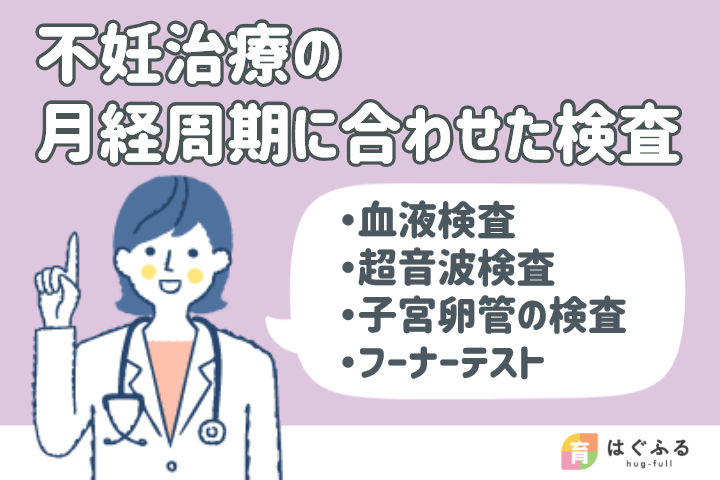
どうして月経周期に合わせて検査をするの?
妊娠にかかわるホルモンには、いくつかの種類があります。それらのホルモンの分泌量の変化によって、排卵が起こったり、月経が起こったりします。
ホルモンの分泌量が足りなくても、逆に多すぎても体のバランスが崩れてしまいます。
適切な時期に適量のホルモン分泌があり、リズムが生まれることで排卵や月経が起こっているといえます。
月経開始から次の月経開始までの期間を「月経周期」といい、一般的に25〜38日(平均28日)が正常です。
月経が始まってから排卵までは卵胞を育てるホルモンが分泌されるので「卵胞期」や「低温期」といいます。
一方、排卵の後には、受精卵が着床しやすいように子宮内膜を厚くする黄体ホルモンが分泌されて体温が少し上昇するため、「黄体期」や「高温期」といいます。
このように低温期や高温期など、本来のホルモン分泌がさかんになる時期に、該当するホルモンの値を測るのです。月経開始から3日目ごろのホルモン値を基礎値といい、ホルモンのバランスの崩れをみるのに適しています。
また、卵管の検査や子宮の中をみる検査は、妊娠の可能性がない時期(低温期)に行います。月経周期に関係なく、いつでもできる検査もあります。
月経周期とその時期に行う検査
血液検査では何を調べるの?
妊娠にかかわるホルモンについては、月経の時期に基礎値を測ります。
そして、それぞれ適切な時期に、十分にホルモンが分泌されているかどうかを調べます。
また、血液検査では、妊娠を妨げる要因となりうるホルモンや物質についても調べます。
・プロラクチン(乳汁分泌ホルモン)
・甲状腺ホルモン検査
・クラミジア検査
・抗精子抗体検査
女性が抗精子抗体を持っていると、精子を異物ととらえて受け入れないことがあり、不妊の原因になることがあります。
・AMH検査
血液検査で調べることができます。
必要な検査を受けるために何回くらい通院が必要ですか?
その人の月経周期に合わせて検査を行っていきます。そのため必要な検査が終わるまでには、1〜3カ月ほどかかります。
検査がすべて終わっていなくても、タイミング法などの治療を受けることは可能です。
最短で、月経中に1回、月経後〜排卵前に1回、排卵後に1回の3回受診すれば、必要な検査はほとんど行うことができます。
病院によって予約制の場合は、次の周期で検査を行うことがあります。
また保険でできる検査と自費の検査は同じ日にできないので、受診日が増えることがあります。
《 監修 》
-
洞下 由記(ほらげ ゆき) 産婦人科医
聖マリアンナ医科大学助教、大学病院産婦人科医長。2002年聖マリアンナ医科大学卒業。
不妊治療をはじめ、患者さんの気持ちや環境を一緒に考えてくれる熱血ドクター。日本産科婦人科学会専門医、日本生殖医学会生殖医療専門医。専門は生殖内分泌、周産期、がん・生殖医療。
▶HP https://www.marianna-u.ac.jp/hospital/reproduction/ 聖マリアンナ医科大学病院
洞下由記先生の監修記事一覧(妊娠希望)
📖妊娠希望に掲載中の記事
【本サイトの記事について】
本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます. Unauthorized copying prohibited.



 妊娠希望の記事を検索
妊娠希望の記事を検索