【医師監修】不妊治療 の検査「女性の場合、初診の検査ではどんなことをするの?」
2020.01.31
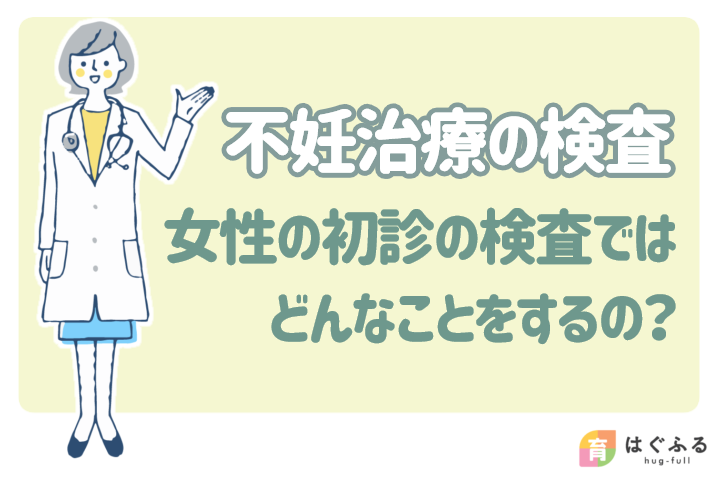
初診ではどんなことをするのですか?【監修:洞下 由記(ほらげ ゆき) 産婦人科医】
医療機関によって内容や進め方は違いますが、初診はおおむね以下のように進みます。
①問診票への記入
診察の前に問診票を渡されるので、それに記入します。
[問診票の内容]
・既往歴、服薬中の薬、アレルギーの有無
・月経の状態(周期、日数、量など)
・子どもを望んでからの期間
・セックスの頻度
・妊娠・出産・流産・中絶の経験 など
②問診
記入した問診票をもとに、毎月の月経の状態や妊娠を望んでからの期間、夫婦生活(セックス)などについて、たずねられます。
今後の治療のための大事な情報となります。
③内診
医師が腹部と膣の双方から圧迫する形で手を使って診察し、子宮や卵巣に大きな異常がないかどうかを確認します。
④超音波(エコー)検査
内診よりも詳細な情報が得られます。子宮筋腫や卵巣囊腫が分かります。時期によっては、卵胞の大きさや内膜の状態から、排卵日を予測できます。
📖関連記事:エコー検査で行うことは?
⑤血液検査
受診した時期によっては、妊娠に関係するホルモンについても調べます。
上記の全てを受けなければいけないわけではありません。
月経の時期によって行うことができる検査が違うので、全ての検査を終えるのに1〜3カ月かかることがあります。
検査や治療について分からないことがあれば、質問しましょう。
医師に聞きにくい場合は、看護師さんに聞いてもかまいません。
クリニックに持って行くものはありますか?
基礎体温をつけていたら持参しましょう。
なくても大丈夫です。
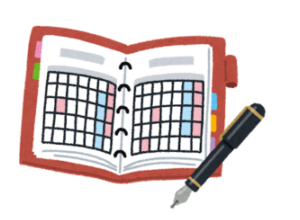
日ごろから、月経の始まった日と終わった日(月経の日数)を手帳などにメモしておくといいでしょう。
最近はスマートフォンのアプリを利用している人も多いので、アプリに記録していれば、それを見せてもいいでしょう。
妊娠を希望してから半年ですが、いつ受診すればいいですか?
妊娠を望んでいるのなら、いつ病院を受診してもかまいません。
まずは妊娠しにくい原因がないかどうか、調べてみることが大事です。
男女ともに特に問題がなければ、しばらく様子をみることもできますし、
排卵を確認するだけの治療(タイミング療法といいます)をすることもできます。
一般的には1年間、排卵日に合わせて性交渉をしても妊娠しない場合は「不妊症」と定義されます。
妊娠を望んでから1年を目安に受診しましょう。

妊娠しにくい要因があったり、タイミングのはかり方(排卵日)を勘違いしている場合もあります。
また、受診のタイミングは女性の年齢でも変わります。
女性の年齢が35歳以上の場合や婦人科の病気がある場合は、期間にはこだわらず、早めに病院を受診しましょう。
生理周期(月経周期)のどの時期に行けばいいですか?生理の時期は受診しないほうがいいですか?
月経周期(月経開始から次の月経開始までの期間)のいつ受診してもかまいません。
それぞれの時期でできる検査があります。
例えば、月経時期や排卵後の高温期には妊娠にかかわるホルモン値を測れますし、排卵時期なら卵胞の成長度合いや子宮内膜の厚さなどを確かめられます。
事前予約制のクリニックもありますが、そうした場合でも特に注意がなければ、月経周期によって予約を変えることはしないでしょう。
「生理だから」
「排卵するかも…」
「高温期に行っても意味がないのでは?」
と考えてためらううちに、受診の機会を逃してしまうことのないようにしましょう。
女性は年齢が上がるほど妊娠しにくくなります。先送りしないで、まずは妊娠に適した状態かどうか、病院で検査をしましょう。
《 監修 》
-
洞下 由記(ほらげ ゆき) 産婦人科医
聖マリアンナ医科大学助教、大学病院産婦人科医長。2002年聖マリアンナ医科大学卒業。
不妊治療をはじめ、患者さんの気持ちや環境を一緒に考えてくれる熱血ドクター。日本産科婦人科学会専門医、日本生殖医学会生殖医療専門医。専門は生殖内分泌、周産期、がん・生殖医療。
▶HP https://www.marianna-u.ac.jp/hospital/reproduction/ 聖マリアンナ医科大学病院
洞下由記先生の監修記事一覧(妊娠希望)
📖妊娠希望に掲載中の記事
【本サイトの記事について】
本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます. Unauthorized copying prohibited.



 妊娠希望の記事を検索
妊娠希望の記事を検索