不育症を起こす 染色体異常 ・子宮奇形とは?検査や治療方法は?【医師監修】
2020.06.08
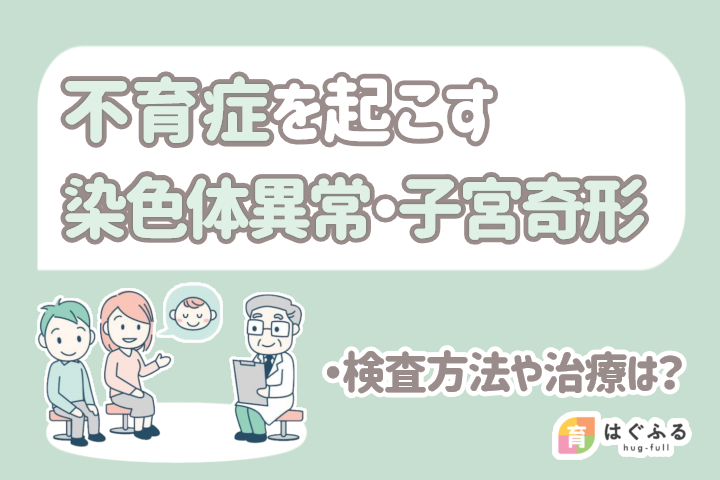
染色体異常とは【監修:洞下 由記(ほらげ ゆき) 産婦人科医】
染色体とは、次世代に遺伝情報を伝える生物に欠かせない物質で、人間は細胞の中に2本ずつ23セット、合計46本の染色体を持っています。
精子と卵子は減数分裂をしてできるので、染色体は1本ずつ23セット、合計23本になります。
精子と卵子が受精すると1個の受精卵となって、また46本に戻ることで、両親の遺伝情報を引き継ぎます。
流産・不育症に関わる染色体異常としては、胎児の染色体に異常がある場合と、夫婦のどちらかの染色体の構造に異常がある場合があります。
胎児の染色体異常は母体の年齢と深い関わりがあり、高齢であるほど胎児の染色体異常が起きやすくなります。
胎児が染色体異常だと、妊娠しなかったり流産したりします。
その結果、加齢により妊娠率が低下したり、流産率が上昇したりすることになります。
染色体の異常の多くは本数の異常で、本来は2本の対である染色体が1本足りない(モノソミー)、1本多い(トリソミー)などがあります。
21番染色体が1本多いのがダウン症候群です。
一方、親側の染色体の異常は、染色体異常ではなく構造異常であることが多いのです。
相互転座や逆位、部分欠失、重複などがあり、どの染色体のどの部分が異常かによって、症状が変わってきます。
胎児の染色体異常
流産の60〜80%は胎児(受精卵)の染色体異常によるものといわれています。
これは自然に起こるもので、防ぎようはありません。
胎児の染色体異常は、母体の加齢とともにその割合が高くなります。
卵子は本人が生まれたときからずっと卵巣に保管されているため、長い時間の中で染色体の構造が不安定になり、染色体異常が起こりやすくなるのです。
胎児の染色体検査は、自費診療になりますが、流産や死産の際の胎盤の組織などを使用して検査することができます。
夫婦の染色体異常
夫婦のどちらかの染色体の構造の一部に変化がある(均等型転座など)場合、減数分裂のときに染色体に過不足が生じることがあります。
そのような卵子や精子が受精し、着床した場合は流産の原因となります。
流産を起こしやすい染色体の構造異常としては、相互転座やロバートソン転座があります。
それらの異常があっても本人の健康には問題がなく、転座があるかどうかは染色体検査(血液検査)をしなくては分かりません。
染色体異常の根本的な治療はなく、以前はうまくいくまで何回でも妊娠にチャレンジすることしかできませんでした。
しかし、着床前診断という方法で、妊娠前に流産を起こす異常があるかないかが分かるようになりました。
まず体外受精を行い、受精卵の染色体や遺伝子の検査をし、異常のないものを子宮に戻すという方法です。
この技術は男女産み分けや優生思想などの危険があるため、倫理的に慎重に検討する必要があります。
着床前診断で正常な染色体の受精卵を子宮に戻しても、妊娠率は100%にはならず、流産率は0%にはなりません。
染色体異常のみが妊娠流産の原因ではないからです。
子宮奇形とは
子宮奇形の検査と治療
《 監修 》
-
洞下 由記(ほらげ ゆき) 産婦人科医
聖マリアンナ医科大学助教、大学病院産婦人科医長。2002年聖マリアンナ医科大学卒業。
不妊治療をはじめ、患者さんの気持ちや環境を一緒に考えてくれる熱血ドクター。日本産科婦人科学会専門医、日本生殖医学会生殖医療専門医。専門は生殖内分泌、周産期、がん・生殖医療。
▶HP https://www.marianna-u.ac.jp/hospital/reproduction/ 聖マリアンナ医科大学病院
洞下由記先生の監修記事一覧(妊娠希望)
📖妊娠希望に掲載中の記事
【本サイトの記事について】
本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます. Unauthorized copying prohibited.



 妊娠希望の記事を検索
妊娠希望の記事を検索